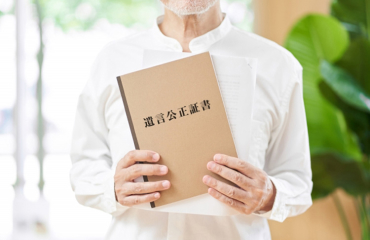ブログBLOG
遺産の相続手続きの期限は?

遺産の相続とは
遺産相続とは、亡くなった人の財産を相続人に引き継ぐ手続きのことをいいます。
役所への死亡届等の手続きや、相続人の調査および範囲の確定、相続財産の調査、遺言がない場合は遺産分割協議など様々な手続きを行う必要があります。
そのような手続きの中には期限が設けられているものもあります。
相続は人の死亡によって開始します。人が死亡すれば、相続人について相続が開始し、遺産は相続人による共有が始まることになります。
相続開始後の手続きの期限について
地方公共団体、日本年金機構への手続き
死亡届とはご家族や同居人が亡くなった際に、その事実を市区町村役場に届け出る手続きです。亡くなった方の同居人などに、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが義務付けられています。死亡者の住所地の市区町村役場は届出先とはなっていませんので、注意が必要です。
火葬許可証とは、故人を火葬するのに必要な許可証で、市区町村役場から発行されます。火葬許可証の取得に必要なのが、「火葬許可申請書」です。
火葬許可申請書の提出期限は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3カ月以内)です。法律で「火葬許可証」がなければ火葬が行えない仕組みになっており、火葬を行う際は必ず必要となる書類です。
世帯主の変更届の提出は14日以内に行わなければなりません。
世帯主変更届とは、住民票に登録されている世帯主が死亡した場合に新しい世帯主へと変更を行う手続きのことです。
国民年金等の受給停止手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。
受給を停止するには、年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給者死亡届」を提出します。手続きには死亡した人の年金証書、死亡の事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)も必要です。
相続放棄
相続財産には土地や建物などの不動産、預貯金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、買掛金や保証債務などのマイナス財産があります。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多ければ、相続放棄を選択した方がよいかもしれません。
相続放棄とは被相続人の資産と負債を一切相続しないことです。
相続を放棄することによって、その相続に関しては、はじめからなかったものとみなされます。
つまり相続人でなかったことになり、被相続人の資産も負債も一切承継しないこととなります。
相続放棄は家庭裁判所に申述します。申述期間は、民法により自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならないと定められています。なお、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
なお、相続放棄は撤回することができません。一度相続放棄が承認されてしてしまうと、その後でプラスの財産があるとわかっても撤回できませんので相続財産の調査は慎重に行いましょう。
相続放棄を行うと相続権に順位変動が起こります。被相続人の両親や兄弟姉妹との人間関係に影響が出る可能性がありますので注意が必要です。親族との関係性への配慮から相続放棄については後順位の相続人(被相続人の両親、兄弟姉妹等の相続人)と足並みをそろえることをおすすめいたします。
準確定申告
亡くなった人に確定申告が行わなければならない場合は、相続人が代わりに手続きを行う必要があります。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
相続税
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月5日に死亡した場合にはその年の11月5日が申告期限になります。
申告期限の日が土曜日、日曜日、祝日などの休日である場合は、これらの日の翌日が申告期限の日とみなされます。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税などのペナルティを科せられる場合がありますので注意が必要です。
相続税の申告書の提出先は、被相続人が亡くなったときの住所を管轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
相続税の申告書は、e-Taxによる電子申告する方法のほか、郵便や信書便による送付または税務署に持参する方法により提出することができます。
税金は金銭で一括納付が原則ですが、相続した財産が予想以上に多かったり、現金の用意が難しいなど期限内での支払いが難しい場合は、延納・物納を使い、相続税の支払いを先延ばしにしてもらえる制度があります。
延納は何年かに分割して納めることです。物納は相続税を金銭で納付することが困難な場合相続などで取得した財産そのもので納めることです。
なお、この延納、物納をする場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書等を提出して許可を受ける必要があります。
相続登記
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
①相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
①と②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら登記の申請をしましょう。
まとめ
相続手続きには期限が定められているものがあり、期限を過ぎるとペナルティが課せられたりしますので早めに手続きをする必要があります。
相続手続きに不安や心配のある方は専門家に相談することをお勧めいたします。
大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市で行政書士をお探しの方
相続手続き 遺言作成 家族信託 相続登記 見守り契約 成年後見契約 遺産分割
協議書の作成 死後事務委任契約 終活 エンディングノートの作成は、ぜひ浜田政克行政書士事務所にご相談ください。