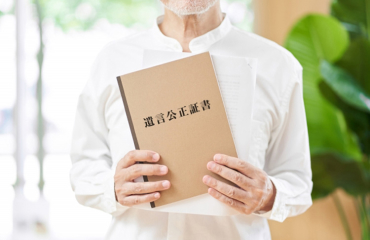ブログBLOG
養子縁組した場合の相続手続き

養子縁組とは
養子縁組は、親子関係のない者同士に、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。
法律上の親子関係になるためには養子縁組の届出が必要です。
養子縁組は2種類あります。
養子縁組には、養子縁組後も実親子関係が存続する「普通養子縁組」と養子縁組により実親子関係が終了する「特別養子縁組」の2種類があります。
特別養子縁組は、こどもの利益のために特に必要がある場合に限り、家庭裁判所の手続により成立します。また、普通養子縁組であっても未成年者を養子とする場合には家庭裁判所における許可等が必要となります。
養子の相続権
養子縁組をした養子は、養親と法律上の親子関係となるため相続権が発生します。
そのため養親が亡くなった際に相続人となり財産を相続することができます。
養子と実子の相続割合
被相続人に実子と養子がいる場合、相続が発生したときはどちらも第1順位の法定相続人となり、法定相続分も同じ割合になります。
例えば、養親が死亡し、養親の相続人として実子が1名、養子が1名いた場合、子2名はそれぞれ2分の1ずつの相続分となります。
養子縁組する際の3つの事例
①孫を養子にする
孫は法定相続人ではないため、養子縁組することによって法律上の親子関係ができますので実子と同順位の第1順位で相続することが可能になります。
生前贈与によって財産を譲る方法もありますが、1年間に受けられる非課税が110万円という制限があります。
養子縁組すれば、実子と同じ立場となり、相続する権利を与えることができます。
②子の配偶者を養子にする
自分の子の配偶者を養子にすることによって、相続人とする方法もあります。
たとえば、子の配偶者がとても献身的に介護をおこなってくれたといった場合に、財産を相続させたいために養子縁組して相続権を与える方法があります。
養子縁組することで第1順位となるため、相続する権利を与えることができます。
③再婚した妻の連れ子を養子にする
再婚した妻に連れ子がいたとしても、血縁関係がないため配偶者でない連れ子は、原則として相続権はありません。
なぜなら、再婚しても自動的に親子関係は成立しないためです。
自分の財産を再婚相手の連れ子にも相続させたいという場合、連れ子に相続権を与える方法として連れ子を養子にするという方法があります。
養子縁組で氏(苗字)はどうなるの?
養親と養子は、お互いに相手を扶養する義務を負います。 養子の氏が養親の氏に変更されます。 養親が死亡したときは、養子は養親の相続人になります。 養子が死亡したときは、その養子に子や孫などがいなければ、養親が養子の相続人となります。
相続で養子縁組をすると節税になる
相続税の基礎控除額が増える
基礎控除とは相続税の計算をする際に相続財産から差し引くことができる金額をいいます。
多くの相続において、相続財産より基礎控除額の方が大きいため課税価格がゼロ円になり、相続税の納付が不要になります。
法定相続人の人数によって、基礎控除額の金額が変わります。相続人が多ければ多いほど基礎控除額も多くなります。
基礎控除額は、【3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)】という計算式で計算されます。
養子縁組をすることによって法定相続人の数が増加して基礎控除額を増やすことができます。
相続を放棄した人も法定相続人の数に含まれます。
養子も法定相続人に数に含めることができますが、被相続人に実子がいた場合は法定相続人になれる養子は1名まで、被相続人に実子がいなかったん場合は法定相続人となれる養子は2名までが上限となっています。
生命保険を活用して節税できる
被相続人が亡くなったときに、指定された受取人が死亡保険金を受け取ります。
この死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象とはなりません。
また、死亡保険金は非課税額を控除することができます。
死亡保険金の非課税限度額は、【法定相続人の人数×500万円】という計算式で計算されます。
そのため、養子縁組をすることによって法定相続人の数が増加して死亡保険金の非課税限度額を増やすことができます。
養子も法定相続人に数に含めることができますが、被相続人に実子がいた場合は法定相続人になれる養子は1名まで、被相続人に実子がいなかったん場合は法定相続人となれる養子は2名までが上限となっています。
相続対策で養子縁組をする際に気を付けること
相続人が増えて一人あたりの相続財産が減る
養子縁組をした養子は、養親と法律上の親子関係となるため相続権が発生します。
そのため養親が亡くなった際に相続人となり財産を相続することができます。
つまり養子縁組をすることによって法定相続人の人数が増えることになりますので法定相続人の一人あたりの相続財産が減ることになります。
養子以外の他の相続人にとっては養子縁組によって法定相続分が減ることになりますので、快く思わない相続人も出てくる可能性があります。
相続税額の2割加算の対象となることがある
養子縁組をすると養親と法律上の親子関係となるため相続権が発生し、第1順位の法定相続人となります。
被相続人の養子は、第1順位の法定相続人であることから、相続税額の2割加算の対象となりません。
しかし孫と養子縁組を行い、相続開始のときに孫が代襲相続人ではない(実子である孫の親が生存している)場合は相続税額の2割加算の対象となるため注意が必要です。
相続税額の2割負担の対象になると第1順位の他の相続人と同額の財産を相続していたとしても相続税額の負担が重くなります。
まとめ
養子縁組は、親子関係のない者同士に、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。
また節税対策に有効である一方で相続税額の2割加算や相続人間でのトラブルの原因となることもありますので注意が必要です。
養子縁組を検討されている方で相続に対する不安や心配がある方は専門家へ相談することをおすすめいたします。
大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市で行政書士をお探しの方
相続手続き 遺言作成 家族信託 相続登記 見守り契約 成年後見契約 遺産分割
協議書の作成 死後事務委任契約 終活 エンディングノートの作成は、ぜひ浜田政克行政書士事務所にご相談ください。