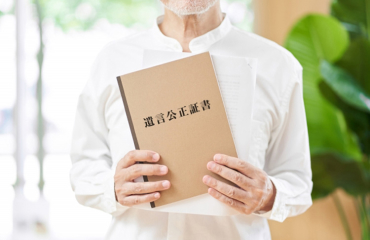ブログBLOG
認知症の相続人がいる場合の相続手続き

相続人の中に認知症の人がいる場合の問題点
相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きはどのように対処すればよいのでしょうか?
遺産分割協議ができない
被相続人に遺言書がない場合、遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議とは相続財産について、誰が何を取得するのか、どれぐらい取得するのか、相続財産の分割割合を法定相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人の全員が遺産分割の内容やその効果を十分に理解できる意思能力、判断能力を有していることが要件となります。
相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を行うことができません。
認知症の程度についての確認
認知症の症状はさまざまで軽度の症状の場合は、意思能力、判断能力を有している場合があります。
この場合は遺産分割協議に参加することができます。
この判断は医師によってのみ行われます。
医師の診断により意思能力、判断能力に問題がないことが証明されれば遺産分割協議を行うことができます。
問題なしとされれば、遺産分割協議を行うことも可能となります。
認知症の判断については念のため、専門の医療機関のサービスを受けるなどの検討も必要となります。
相続放棄について
認知症を発症して判断能力が低下すると、法律行為をすることができなくなります。認知症の相続人が自ら相続放棄をすることはできません。他の相続人が代理人となって家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うこともできません。
成年後見制度
認知症や知的障害、精神障害など、ひとりで決めることに不安や心配な方、判断能力が衰えた方の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行うために定められた国の制度を成年後見制度といいます。
成年年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
・法定後見とは、本人の判断能力が低下してしまった方、または判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度です。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が衰えた方は、日常の生活においてさまざまな問題に直面します。預貯金や不動産など自身の財産を管理することが難しく、介護や福祉のサービスに対して自分で適切な契約ができなかったりします。またこのような方を対象にした悪質商法による被害に遭うことが考えられます。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
・任意後見は、自分自身が元気なうちに、この先あれこれ決められなくなる前に、将来の支援者と支援の内容をあらかじめ定めて自分らしい生き方を自ら決めるための契約をしておく制度です。
支援が必要な人を「本人」、支援する人を「任意後見人」といいます。
利用方法は法律で決められています。
任意後見制度を利用するには、支援者との間で公正証書によって任地後見契約を締結します。
やがて本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所への申立てによって任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されます。これによって任意後見が開始します。
成年後見制度の注意点
・本人や家族が希望する方が法定後見人にならない可能性がある
法定後見人の選任では、法定後見人の希望を裁判所に伝えることができます。しかしながら本人や家族が希望する法定後見人にならないこともあります。法定後見人は、家庭裁判所が選任をします。民法での欠格事由に該当する人物でなければ、だれでも法定後見人になることができます。法定後見人に特別な資格は不要です。しかし、親族を法定後見人の候補者として申立てをしても、最終的には家庭裁判所が判断をします。被後見人の所有財産が多額である場合や、家族間トラブルがあるような場合には、裁判所は、法律の専門家である弁護士や司法書士を選任する傾向にあります。
・申立て費用や後見人報酬が発生する
家庭裁判所に後見等開始の申立てを行う場合と後見業務が開始されてから以下の費用が発生します。 ・申立てから後見人等が選任されるまでの手続き費用 申立てから後見人等選任までの費用 ・後見人等の報酬(制度利用中は常時発生) 成年後見制度の申立費用は、成年後見制度を利用する本人ではなく申立者が負担します。 しかし、成年後見制度の利用が開始された後に、申立者は制度利用者本人に対してかかった費用を請求可能です。 成年後見制度の利用は申立者本人の利益につながる行為ではなく、制度利用者本人の利益につながる行為だと考えられるからです。
・成年被後見人の財産を自由に使うことができなくなる
成年被後見人の財産は保全の対象となります。したがって自由な運用や活用および処分(売却)はできなくなります。相続税対策としての生前贈与も認められません。 成年後見人は、成年被後見人の財産に関する様々な契約や手続きを代理する権限を与えられています。 そして成年後見人は、本人の利益のために本人の資産を使う法律上の義務があります。
・法定後見が不正を起こすことがある
家庭裁判所が公開している情報では、後見人等による不正事例において、令和5年では184件、約7億円の被害額となっています。専門職の内数になると令和5年で29件、約2億7千万円となっています。後見人による不正の大半は親族後見人によるものとなっています。 このようなことから成年後見制度においては後見人による不正が起こらないように対策が講じられていくのですが、家庭裁判所が適切に監督権限を行使させることが有効になります。 成年後見制度において、成年後見人と共に成年監督人が選任されることに納得しますね。 また専門職が選任されることが増加傾向にあることも理解できます。
・原則として途中でやめることができない
一度、成年後見制度を利用すると途中でやめることはできません。医者が書いた診断書で障害や症状の回復が認められて家庭裁判所で成年後見の取消が認められるとやめることができます。
多くは、後見制度を途中でやめることができずに、被後見人が死亡するまで続くことになります。
成年後見制度は認知症になった人の生活に必要不可欠な制度ですが、デメリットを十分に理解した上で制度利用の検討をする必要があります。
法定後見制度の利用
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が衰えた方は、日常の生活においてさまざまな問題に直面します。預貯金や不動産など自身の財産を管理することが難しく、介護や福祉のサービスに対して自分で適切な契約ができなかったりします。またこのような方を対象にした悪質商法による被害に遭うことが考えられます。
法定後見とは、本人の判断能力が低下してしまった方、または判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度です。
法定後見制度は3つの類型に別れています。
法定後見制度は、支援が必要な方の判断能力の度合いに応じて、「後見」「補佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
・後見:多くの手続、契約などを、ひとりで決めることができない方
・補佐:重要な手続、契約などを、ひとりで決めることが心配があり、常に援助が必要な方
・補助:重要な手続、契約の中で、ひとりで決めることに心配があり、援助が必要な場合がある方
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
法定後見制度において後見人は、本人のために適切な財産管理を行います。
本人のために支払いをしたり、収入を受け取ったり、財産の管理を行います。収入や支出は通帳や現金出納帳で漏れの無いように管理します。
遺産分割協議においても本人の代理人として参加することができます。
まとめ
被相続人に遺言書がない場合、遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人の全員が遺産分割の内容やその効果を十分に理解できる意思能力、判断能力を有していることが要件となります。
よって相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を行うことができません。
相続人の中に認知症の方がいる場合は、遺言書を作成することをおすすめいたします。
また相続人の中に認知症の方がいて不安や心配のある方は専門家に相談することをおすすめいたします。
大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市で行政書士をお探しの方
相続手続き 遺言作成 家族信託 相続登記 見守り契約 成年後見契約 遺産分割
協議書の作成 死後事務委任契約 終活 エンディングノートの作成は、ぜひ浜田政克行政書士事務所にご相談ください。