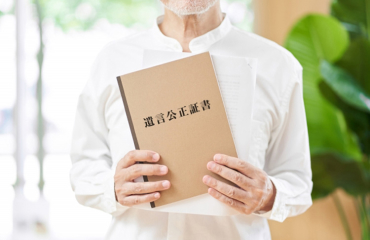ブログBLOG
ペットに遺産を相続させることができる?ペットを引き取ってもらう対策

ペットに財産を相続できる?
私が子供の時は、ペットより自分が早く亡くなるとは思いもしませんでした。
現在は犬を飼っていますが、今の私はそれなりに歳を重ねてしまい少し自信がありません。
飼い主がなくなってしまい、ペットがだれからも面倒をみてもらえないということはとても気がかりですよね。それだけは絶対に回避したいところです。
ペットに財産を相続させたいと思っても日本の法律では人以外に財産を相続することはできません。
ペットはとても大切な家族ですが、法律上は「動産」という扱いになり、法的に権利能力を有する権利の主体とはなりえません。
動産とは、土地及びその定着物(建物)以外の有体物のことです。
ですから残念ながらペットは相続人や受遺者になることはできないのです。
ペットは相続財産になる?
犬や猫などのペットは動産という扱いになるので相続財産として取り扱われます。
被相続人の相続開始に伴い、遺産として相続の対象となりますので遺言書でペットの相続について記載することができます。
原則として、ペットには財産としての価値がありません。
ペットに財産的な価値がない場合は、遺産分割協議ではなく、形見分けのように関係者による話し合いで引き取りを検討することが一般的なようです。
相続においては遺言書で付言事項としてペットの世話をしてもらえるように相続人または第三者に依頼をすることになります。
例外的に、血統書付きでペットで市場価格が高額な場合は場合には財産価値があり、相続税の対象となる場合があります。
ペットを相続人や第三者に引き取ってもらうための対策
ペットの面倒をみてくれる人を探してきて、世話をしてくれることを条件に自身の財産を譲るという方法を取ることが出来ます。
そのために、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与契約」などの方法があります。
負担付遺贈とは、遺言者が受遺者に対して財産を譲渡する見返りに一定の義務を負担してもらう遺贈のことをいいます。財産の受遺者に一定の役割を引き受けてもらうと解釈してください。
ペットの負担付遺贈は、残されたペットの飼育をしてもらう代わりに、飼育を引き受けた人に財産を相続させることです。この場合、生前にペットの新しい飼い主をあらかじめ決めておかなければなりません。そのうえで遺言書などに誰に何を依頼して、何を遺贈するかをしっかり明記しておく必要があります。
ただし、問題点として遺贈は一方的な意思表示なので、相手の同意は必要がないことです。遺言をするだけでできるため、受贈者が受け取りを放棄することもできます。遺贈を放棄する場合、受贈者は財産を受け取ることができませんが、ペットの飼育を拒否することができます。
負担付死因贈与契約とは財産を贈る贈与者と、受け取る受贈者が、生前から贈与内容について契約を取り交わすものです。一方的に遺言をするだけでもできる負担付遺贈と異なり、死因贈与は契約となっており特段の事情がない限り撤回をすることができなくなっています。そのため、負担付遺贈では自分の死後にペットの飼育を本当に請け負ってもらえるかどうか心配という場合は、負担付死因贈与契約の方がよいでしょう。
負担付死因贈与契約を取り交わす際は、口頭で約束を交わすだけでなく、お互いにきちんと書面にして契約書として締結しておくことが必要です。
負担付遺贈は飼い主が死亡したときから効力を生じます。負担付死因贈与契約だと飼い主が生きているうちからペットの世話をお願いすることが可能となっています。このあたりが負担付死因贈与契約のメリットとなります。
まとめ
いずれにしてもペットを最期まで飼うという責任が飼い主にはあると思います。ですからペットの世話をお願いする相手方の人選にも飼い主の責任があるということを忘れてはいけませんね。
ペットの相続について心配や不安がある方は当事務所に相談することをおすすめいたします。
大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市で行政書士をお探しの方
相続手続き 遺言作成 家族信託 相続登記 見守り契約 成年後見契約 遺産分割
協議書の作成 死後事務委任契約 終活 エンディングノートの作成は、ぜひ浜田政克行政書士事務所にご相談ください。