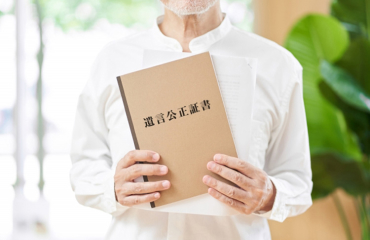ブログBLOG
相続人の中に相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議はどうなるのか?

相続人の中に相続放棄した人がいる場合
相続放棄とは
被相続人が亡くなって相続を開始する際に、遺言書がなければ遺産分割協議を行うことになります。被相続人の相続手続きを進める際に相続人のうちの1人が相続放棄をすることがあります。
相続放棄の理由はさまざまです。
・借金があるかもしれないと心配になっている
・被相続人と疎遠のため相続財産はいらないを思っている
・他の相続人と疎遠のため遺産分割協議で顔をあわせたくない
・自分は相続財産はいらないので自分以外の相続人に財産を相続してほしい
・被相続人の財産を相続するのに負い目を感じている
相続人の中に相続放棄をした相続人がいる場合に遺産分割協議はどのようにして進めたらよいのでしょうか?
また相続放棄には法律上の相続放棄と相続分の放棄(事実上の相続放棄)の2種類があります。
相続放棄
被相続人の資産と負債を一切相続しないことです。
相続を放棄することによって、その相続に関しては、初めからなかったものとみなされます。
つまり相続人でなかったことになり、被相続人の資産を相続する権利も負債を返済する義務も一切承継しないこととなります。
相続放棄は家庭裁判所に申述します。申述期間は、民法により自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならないと定められています。なお、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
なお、相続放棄は撤回することができません。
被相続人の財産の相続にかかわりたくない、他の相続人と顔を合わせたくない場合には家庭裁判所に相続放棄の申述をするという方法が有効です。
相続分の放棄
家庭裁判所に相続放棄の手続きをとらなくても相続人が相続財産を放棄することはできます。
遺産分割協議で自身が相続財産を取得しないことに同意し、遺産分割協議を成立させる方法があります。
遺産分割協議書で自身の相続分は取得しないことに合意し、遺産分割協議書に署名・捺印します。
そうすれば実印と印鑑証明書の準備は必要となりますが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするよりもずっと負担が少なくてすみます。
事実上の相続放棄は、遺産分割協議書を利用して相続放棄と同様の効果を得ることができますが、裁判所に申述する相続放棄とは異なり、法定相続人でなくなることはありません。
もし債権者から借入金等の返済を要求された場合には応じるなければなりません。
また、相続人でありつづけることに変わりはありませんので、被相続人の思い出となる遺品とか肩身を受け取ることができます。
事実上の相続放棄のことを相続分の放棄といいます。
相続放棄をした相続人がいる場合の遺産分割協議
相続放棄の場合
家庭裁判所に相続放棄の申述をした相続人は、その相続に関しては、はじめからなかったものとみなされます。
つまり相続人でなかったことになり、被相続人の資産を相続する権利も負債を返済する義務も一切承継しないこととなります。
相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため相続放棄をした相続人は遺産分割協議には参加することができなくなります。
従って相続放棄をした相続人を除いた相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議後の相続手続きでは預貯金の解約払戻しや法務局での不動産名義変更では必要書類を提出することになります。
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合には、必要書類である相続関係を証明する戸籍謄本一式や遺産分割協議書や印鑑登録証明書などに加えて、相続放棄をした方の相続放棄申述受理証明書を提出します。
※相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄をしたことを第三者に証明するための書類で、裁判所に交付申請すると発行してもらえます。
相続分の放棄の場合
事実上の相続分を放棄するには、他の相続人とともに相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議の中で財産を相続しないという意思表示を他の相続人に対して行います。
財産を相続しないという意思表示を、他の相続人に了承してもらって初めて相続分の放棄は成立します。
遺産分割協議書では、相続分の放棄をした相続人がいる旨を記載することが必要となります。また遺産分割協議に参加していますので遺産分割協議書に相続分の放棄をした相続人も署名押印します。
遺産分割協議書を作成する際には、何も相続しない相続人がいることがわかるような記述をしなければなりません。
税務上の影響は
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
基礎控除額を計算する際には、相続放棄はなかったこととして扱われます。 つまり相続人に相続放棄した人がいたとしても、この「法定相続人の数」には影響せず、基礎控除額が変わることはありません。
生命保険の非課税額控除
生命保険金「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠を計算する際には、相続放棄はなかったこととして扱われます。 つまり相続人に相続放棄した人がいたとしても、この「法定相続人の数」には影響せず、非課税枠が変わることはありません。
相続放棄を行った人が生命保険金を受け取った場合、非課税枠の適用が一切ありませんので受け取った生命保険金はすべて相続税の対象となります。
相続分の放棄を行った人が生命保険金を受け取った場合、非課税枠を利用することができます。
税務上の詳細について税理士等に相談しましょう。
まとめ
被相続人が亡くなって相続を開始する際に、遺言書がなければ遺産分割協議を行うことになります。
被相続人の相続手続きを進める際に相続人の中に相続放棄される方がいる場合に相続放棄と相続分の放棄では遺産分割協議の進め方が異なります。
遺産分割協議には期限がありませんが、相続財産の額によっては相続開始を知った翌日から10か月以内に相続税の申告・納税をしなければなりません。
このような場合の遺産分割協議で不安や心配がある方は専門家へ相談することをおすすめいたします。
大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市で行政書士をお探しの方
相続手続き 遺言作成 家族信託 相続登記 見守り契約 成年後見契約 遺産分割
協議書の作成 死後事務委任契約 終活 エンディングノートの作成は、ぜひ浜田政克行政書士事務所にご相談ください。